
建設業許可を取得したいけど、経営業務管理責任者いわゆる経管(けいかん)の要件を満たす人が自社に居ない場合、他の建設会社で取締役だった方を自社に迎えて経管の要件を満たして建設業許可を取得する事があります。
今回は、経営業務管理責任者になり得る方を、自社に迎えて許可取得を目指す場合に準備するものや注意点をご説明させていただきます。
➡ 5分で分かる!大阪府知事 一般建設業許可新規申請 ~法人編~
目次
1.建設業許可要件の経営業務管理責任者とは?
建設業は、完全な受注生産であるため、発注者は完成品を見てから購入するかどうかを検討することが出来ません。
手抜き工事や欠陥があった場合も、外形的に一目見て分かるようなことも稀です。
そして発注金額も高額で、工事も長期にわたって行われることが多く、建設業の経営者は、これらの特殊性を踏まえ多額で複雑な資金の流れを把握し、建設物を完成させる必要があります。
このような事から、建設業許可業者となるためには、一定期間建設業を経営した経験がある者を自社の経営陣に常勤で置くことが求められています。
〇常勤の役員であること
原則として、一月あたり10万円以上の役員報酬が支払われて、健康保険と厚生年金保険への加入が必要となります。
営業所に常勤で働く必要があることから、毎日通勤できないような遠方に住む方は認められません。
〇出向社員が出向先で経管になれるのか
結論から言うと可能です。
可能ですが、出向先でも取締役に就任して登記する必要があり、保険証の書き換えも必要となります。
出向先で取締役になる必要があるため、出向協定を結んで自社に来てもらうメリットは無いと言えるでしょう。
2.経営経験を証明するための書類について
建設業を経営していたことを証明することが出来なければ、例え自社に取締役として迎え入れても建設業許可を取得する事は出来ません。
他社での経営経験がある方に自社の取締役に就任してもらい、建設業許可取得を目指すのであれば、役員の就任登記の前に行政書士にご相談されることをおススメいたします。
〇建設業を営む会社での5年以上の取締役経験の場合
- 法人税の確定申告書(別表一・決算報告書)※経験年数分
- 建設工事の ①契約書 ②注文書・請書 ③請求書のどれか
※経験年数分 工事同士が12か月以上空かないように - 履歴事項全部証明書
- 法人税の確定申告書(役員報酬手当)
〇個人事業で建設業を5年以上営んでいた場合
- 所得税の確定申告書(第一表)※経験年数分
- 建設工事の ①契約書 ②注文書・請書 ③請求書のどれか
※経験年数分 工事同士が12か月以上空かないように
〇建設業許可を受けた建設会社で、経営業務管理責任者だった場合
- 経営業務管理責任者に就任した時の建設業許可申請書 または 変更届 ※受付印と青書きあり
〇建設業許可を受けた建設会社で、経管ではない取締役だった場合
1+4または2+3+4の書類
- 建設業許可申請書か変更届で経営経験分の常勤役員等証明書 ※受付印あり
- 建設業許可通知書(経営年数分)
- 決算変更届(直近分)※受付印あり
- 履歴事項全部証明書
1の書類は、以前役員だった建設会社で、別の役員が経営業務管理責任者として証明されている建設業許可申請書または経営業務管理責任者の変更届です。
2の建設業許可通知書が複数枚準備できる場合は、決算変更届の提示は必要りません。
これらの書類を提示するのは、建設業を適法に5年以上営業していたかを確認する事が目的であるので、建設業許可を更新している=決算変更届も提出し建設業を営んでいたという事になるため、決算変更届を準備して改めて提示する必要が無いという事です。
3.この場合の建設業許可取得難易度について
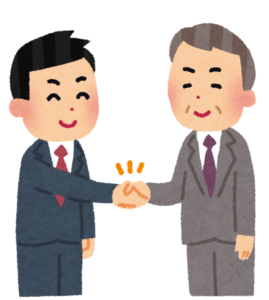 社長ご自身が経営業務管理責任者に就任する場合は、書類が揃うかどうか、経営経験の年数が足りるかどうかが問題になってきますが、他社での経営経験者を取締役に迎える場合に問題となるのが、書類を借りる等の協力を得られるかどうかという事です。
社長ご自身が経営業務管理責任者に就任する場合は、書類が揃うかどうか、経営経験の年数が足りるかどうかが問題になってきますが、他社での経営経験者を取締役に迎える場合に問題となるのが、書類を借りる等の協力を得られるかどうかという事です。
ご準備いただく書類をざっと見てもらったとおり、経営経験の証明のためには、他社の決算書、工事の請求書、建設業許可申請書の副本などを貸してもらう必要があります。
親族で何でも言える間柄だったり、建設業を引退された元社長さんや元個人事業主さんで書類を自由に出来る立場の方だったら良いのですが、そうでない場合は難しい可能性があります。
ですので、自社の取締役に就任してもらう前に、これらの書類を借りる事が出来るのかしっかり話し合っていただければと思います。
4.最後に…
こちらの書類は、大阪府知事許可で経営業務管理責任者になるために準備する必要があるものになります。
他府県で建設業許可を取得する際には、別の書類が必要になる可能性が高いためご注意ください。
もしも建設業許可取得でお困りごとがありましたら、一度メールか電話でお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。





